下田地区消防組合消防無線管理運用規程
昭和58年4月1日
規程第2号
改正 |
平成6年4月5日規程第3号 |
平成14年4月1日訓令第3号 |
目次
第1章 総則(第1条〜第6条)
第2章 責務(第7条〜第9条)
第3章 無線局の構成及び管理(第10条〜第15条)
第4章 通信の種類、運用及び通信統制(第16条〜第19条)
第5章 非常災害時における通信体制(第20条〜第24条)
第6章 訓練等(第25条・第26条)
第7章 簿冊及び諸報告(第27条〜第30条)
第8章 点検及び応急措置(第31条〜第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか消防無線(以下「無線」という。)の適正な
管理及び運用方法を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 無線機器とは、超短波無線電話機及びそれに付随する設備をいう。
(2) 無線機器の管理とは、機器の配置、保守点検及び整備等をいう。
(3) 通信方法とは、無線機器の取扱い、通信連絡の設定及び通信要領をいう。
(4) 無線管理責任者とは、無線局の適正かつ能率的な利用を確保するため電波関係法
令に定める各種手続を行い、無線従事者及び通信取扱者を指揮監督するものをいう。
(5) 通信取扱者とは、第三級陸上特殊無線技師等の資格の無線従事者の操作範囲に属
する無線設備のうち、その技術操作が相手方の無線局の無線従事者により管理される
こととなっている技術操作を行うものをいう。
(無線局の目的)
第3条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第1条に定める消防の任務を遂行するため、
無線局を開局する。
(管理体制)
第4条 消防長は、消防署通信指令室に無線管理責任者を置き、無線局の管理運用及び電
波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)に基づく諸手続き等について、業
務の統一処理を図るものとする。
2 無線局の管理責任者は、消防署係長とする。
(指導)
第5条 無線管理責任者は、無線機器の機能を正常に維持し、かつ、適正な通信の疎通を
図るため、これらの点検、整備通信方法、その他について必要な指導を行わせなければ
ならない。
(基地局の無線機器の操作)
第6条 基地局の無線機器は、無線従事者として専任されている者でなければ、これを操
作してはならない。
第2章 責務
(無線管理責任者の責務)
第7条 無線管理責任者は、無線管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて消防長の
指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければならない。
2 無線管理者責任者は、無線局の管理運用若しくは無線機器の点検及び整備、又は無線
機器の操作、若しくは取扱いに関する監督を行うときは、無線従事者及び無線管理係に
対して、必要な指示を与えなければならない。
3 無線管理責任者は、研修計画及び通信訓練計画を作成しなければならない。
(無線従事者の責務)
第8条 無線従事者は、法に基づき機能を十分発揮するよう適正な運用に努めるとともに、
無線業務日誌の記載等を適切に行わなければならない。
(通信取扱者の責務)
第9条 通信取扱者は、無線機器の通信方法及び操作方法をよく熟知し、適正な管理及び
取扱い技術の向上に努め、その機能を十分に発揮させなければならない。
第3章 無線局の構成及び管理
(無線機器の新設等)
第10条 無線機器を新設、増設、改造、変更及び移設若しくは無線機器の機能に影響を与
えるおそれのある行為をしようとする場合は、消防長の承認を得なければならない。
(無線従事者による通信の管理)
第11条 無線従事者は、法及びこれに基づく規則等に定められた通信方法により、適正な
通信を行わなければならない。
(無線従事者の配置及び勤務体制)
第12条 消防長は、無線局の運用形態に応じて、無線従事者を適正に配置する義務を有す
る。
2 基地局の勤務体制は、無線従事者による交替制とし、これ以外の者が基地局の無線機
器の操作を行わなければならない様な勤務を編成してはならない。
(無線局の構成)
第13条 無線局の構成は、別表第1に定めるとおりとする。
(配置)
第14条 消防長は、無線機器の性能その他を考慮して、適正な配置を決定しなければなら
ない。
2 消防長は、無線機器の配置を決定する場合には原則として、その配置する場所又は車
両等を指定するものとする。
(保守管理)
第15条 消防長は、配置されている無線機器の性能の把握に努めるとともに、常に効果的
に活用できるよう保管の適正を図らなければならない。
第4章 通信の種類、運用及び通信統制
(通信の種別及び優先順位)
第16条 無線通信は、通信内容の緩急と主要度に応じて非常災害時通信及び平常時通信に
区分し、非常災害時通信は平常時通信に優先し、その種別及び優先順位は次のとおりと
する。
(1) 非常災害時通信
ア 災害通報 災害の発生を通報する通信
イ 出動指令 消防隊、救急隊、その他の隊又は消防団に対する出動指令等
ウ 応援要請 消防隊、救急隊、その他の隊又は消防団の応援要請をする通信
エ 指揮命令 災害現場における指揮命令
オ 現場報告 災害状況等の報告
(2) 平常時通信
ア 訓練通信 訓練、演習時における通信
イ 試験通信 無線機の機能試験のための通信
ウ 業務通信 業務連絡等の通信
(無線局の運用)
第17条 消防長は、消防職員に適正な通信方法により、通信を行わせなければならない。
2 無線局の運用の適正を図るため、運用項目を別に定める。
(監視及び検査)
第18条 無線管理責任者は、必要に応じて通信方法等の監視並びに無線機器の機能の良否
及び管理の適否を検査するものとする。
(通信統制)
第19条 消防無線の通信統制は、次の各号の区分とし、通信内容の制限については、別表
第2で定めるとおりとする。
(1) 第1統制 火災等の災害が発生し、通信がふくそうし又はふくそうが予想され通
信統制をする必要があると認められた場合
(2) 第2統制 大規模若しくは、同時に多数の火災等の災害が発生し、又は発生のお
それがあり強力な通信統制をする必要があると認められた場合
(3) 第3統制 消防長が特に必要と認めた場合
2 前項の通信統制は、消防長の指示により行うものとする。
第5章 非常災害時における通信体制
(通信体制の確保)
第20条 消防長は非常災害の発生又は大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)
に基づく警戒宣言が発せられたときは、震災消防活動対策(昭和54年)地域防災計画及
びこれに関連する定めに従い迅速に通信体制を確保しなければならない。
(指揮命令系統)
第21条 陸上移動局に対する指揮命令は、原則として通信指令室において行い、分署基地
局の一括統制を行うものとする。ただし、現場その他通信指令室以外の場所において指
揮命令を行う場合は、通信指令室に指揮命令内容を周知させておかなければならない。
(要員体制)
第22条 基地局における通信勤務員は、2名以上とする。
2 無線管理責任者は、災害時の通信要員体制の確立を期すため、あらかじめ勤務方法を
職員に周知徹底させておくものとする。
3 災害が発生した場合、分署の有線式遠隔制御方式基地局を分署においても直接運用が
図られるように、各分署における無線従事者は1名以上常駐させなければならない。
(陸上移動局の配置)
第23条 消防長は、非常災害が発生したときは、人命保護を最重点とし、災害の状況、復
旧の緊急性及び道路状況等を考慮して陸上移動局を適正な場所に配備しなければならな
い。
2 消防長は、あらかじめ陸上移動局の無線機器の操作者を指定しておかなければならな
い。
3 消防長は、警戒宣言が発せられた場合に、次の各号の事項を実施するため、陸上移動
局が迅速に配備できるようあらかじめ配備計画を立案しておかなければならない。
(1) 情報の収集と伝達
(2) 消火活動、救助活動の出動体制の確立
(3) 危険地域の掌握と対応及び住民への避難勧告又は指示体制の確立
(4) 火気使用制限に関する広報及びパトロールの実施
(5) 資機材の点検整備及び水利の確認と確保
(6) 避難路の確認と確保
(商用電源障害時の電源確保)
第24条 基地局には、商用電源の障害時に備え、予備電源を設置しなければならない。
第6章 訓練等
(通信訓練)
第25条 消防長は、災害時の通信を正常かつ能率的に運用するため無線管理責任者の作成
した通信訓練計画に基づき、3か月に1回通信訓練を行わなければならない。
(消防職員の研修)
第26条 消防長は、消防職員に通信が適正に行われるよう電波関係法令並びに無線機器の
取扱い及び通信方法について無線管理責任者の作成した研修計画に基づき、必要な研修
を年2回以上行わなければならない。
第7章 簿冊及び諸報告
(簿冊等)
第27条 無線機器の保管、点検及び整備に関する記録を整理するため通信指令室には、次
の関係簿冊を備え付けておかなければならない。
(1) 無線機器台帳 (様式第1号)
(2) 総合点検表 (様式第2号)
(3) 精密点検表 (様式第3号)
(4) 無線従事者管理カード (様式第4号)
(5) 無線従事者資格取得報告書 (様式第5号)
(6) 無線従事者免許証記載事項異動報告書 (様式第6号)
(7) 無線従事者免許証亡失報告書 (様式第7号)
(8) 無線機器損傷事故報告書 (様式第8号)
(9) 無線機器亡失事故報告書 (様式第9号)
2 前項の簿冊及び法第60条の規定により備え付けを要する業務書類は、無線管理責任者
が管理する。
3 無線管理責任者は、無線業務日誌(様式第10号)を毎日検印するものとする。
(無線従事者の選解任届)
第28条 無線管理責任者は、法第51条の規定による無線従事者選解任届を遅滞なく行わな
ければならない。
(無線従事者の報告)
第29条 無線従事者が次の各号の一に該当したときは、無線従事者資格取得報告書(様式
第5号)無線従事者免許証記載事項異動報告書(様式第6号)及び無線従事者免許証亡
失報告書(様式第7号)により、10日以内に無線管理責任者を経由して、消防長に報告
しなければならない。
(1) 無線従事者の資格を取得したとき。
(2) 無線従事者免許証記載事項に異動を生じたとき。
(3) 無線従事者免許証を亡失したとき。
(事故報告)
第30条 無線機器の損傷又は亡失事故等が発生したときは、無線管理責任者は直ちに、無
線機器損傷事故報告書(様式第8号)又は無線機器亡失事故報告書(様式第9号)によ
り、消防長に報告しなければならない。ただし、軽易なものについてはこの限りでない。
第8章 点検及び応急措置
(点検の種別)
第31条 消防長は、次の各号に掲げる区分により消防職員に適正な無線機器の点検を行わ
せなければならない。
(1) 定時点検
(2) 使用後点検
(3) 総合点検
(4) 精密点検
(点検の方法及び記録)
第32条 定時点検並びに使用後点検は、無線従事者が次の各号の事項に留意して行うもの
とする。
(1) 数量の確認
(2) 外観、構造の異状の有無
(3) 機能の良否
2 総合点検は毎月1回行うものとし、無線機器台帳(様式第1号)の保守記録欄及び総
合点検表(様式第2号)にその概要を記録しておかなければならない。
3 精密点検は、専門業者に委託して精密点検表(様式第3号)により、年2回行うもの
とし、無線機器台帳(様式第1号)の保守記録欄にその概要を記録しておかなければな
らない。
4 予備装置及び予備電源の機能試験については、3か月に1回以上行うものとする。
(点検実施者の指定)
第33条 消防長は、総合点検及び応急措置を行わせるため、無線従事者のうちから点検実
施者を指定しておかなければならない。
(応急措置)
第34条 無線管理責任者は、無線機器に障害が発生したとき又は発生するおそれのあると
きは、点検実施者に対して速やかに応急措置を行わせなければならない。
2 前項の応急措置を行ったときは、第32条第2項に準じその概要を記録しておかなけれ
ばならない。
附 則
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成6年4月5日規程第3号)
この規程は、平成6年4月15日から施行する。
附 則(平成14年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
別表第1
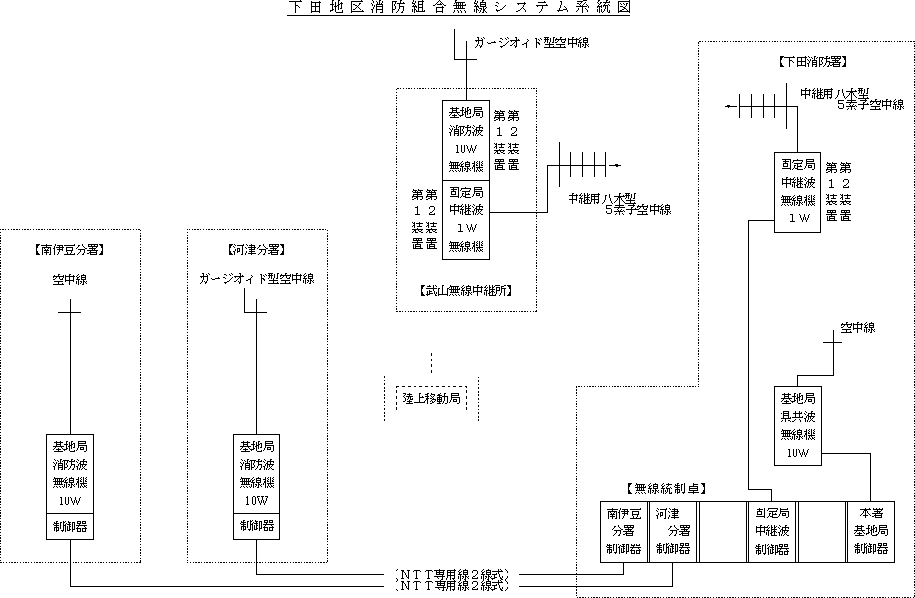 別表第2(第19条関係)
通信統制時における内容制限
別表第2(第19条関係)
通信統制時における内容制限
内容 |
統制時における移動局等の通信事項 |
統制区分 |
火災等 |
救急 |
第1統制 |
1 火災通報 |
1 出動報告 |
2 応援要請 |
2 現着 |
3 現場報告のうち通信指令
室で指示したもの |
3 応援要請 |
|
1 火災通報 |
1 出動報告 |
第2統制 |
2 応援要請 |
2 現着 |
|
|
3 応援要請 |
第3統制 |
通信指令室の呼出しに対し必
要事項のみ応答するもの |
左欄に同じ |
様式第1号
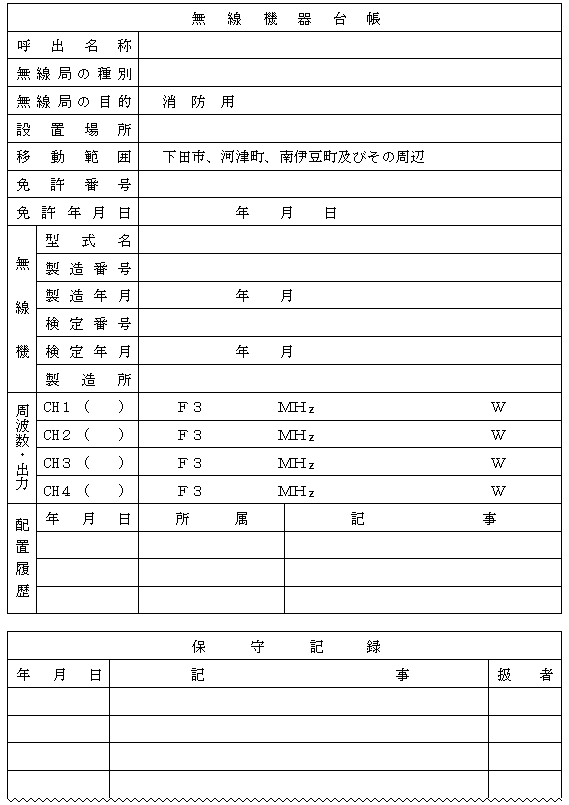 様式第2号
様式第2号
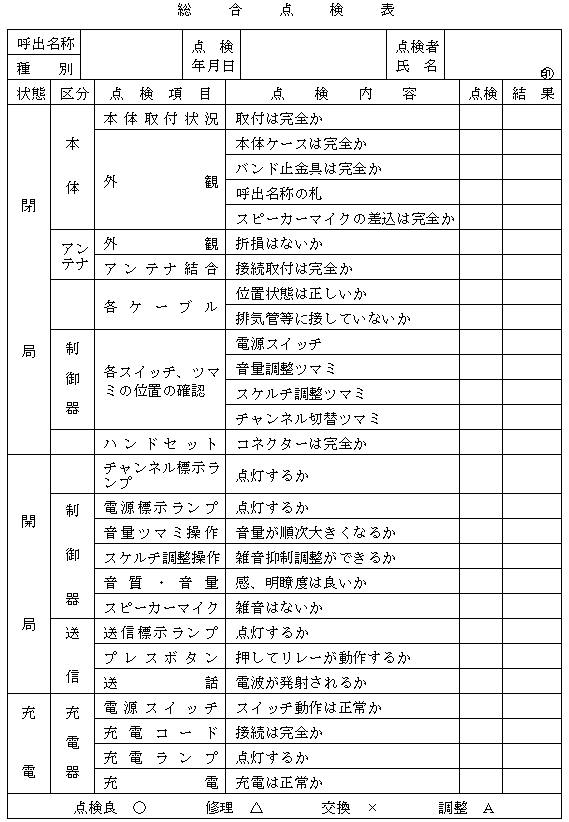 様式第3号
様式第3号
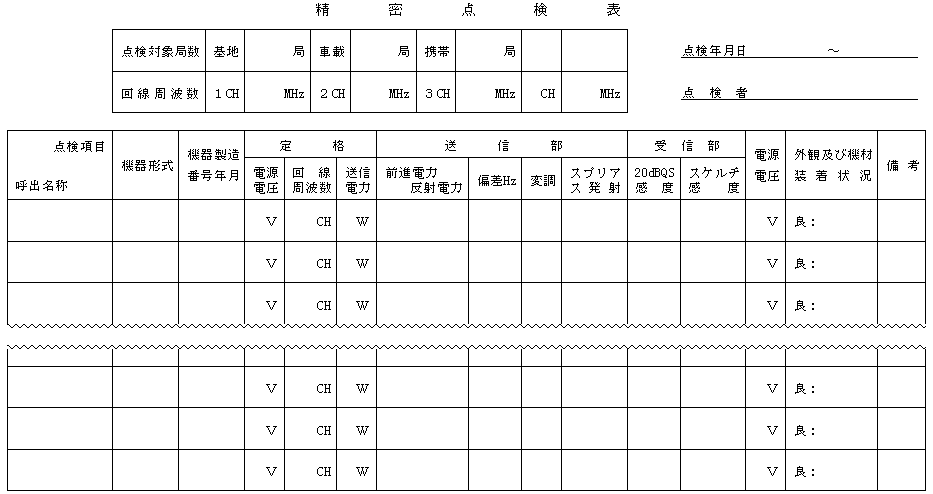 様式第4号
様式第4号
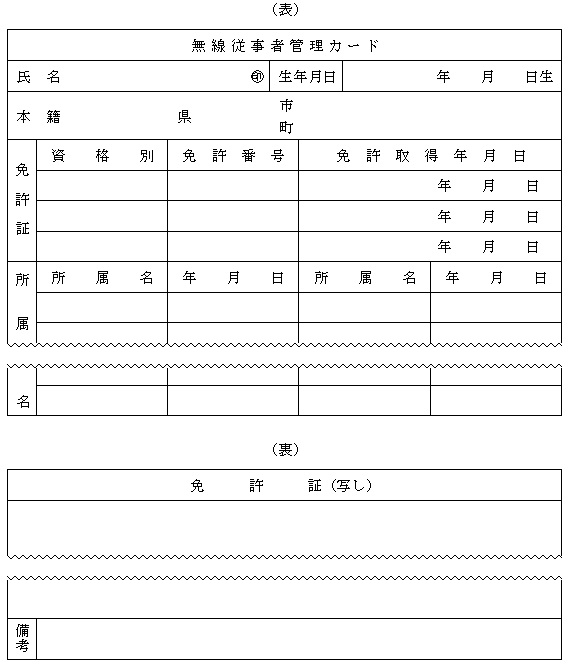 様式第5号
様式第5号
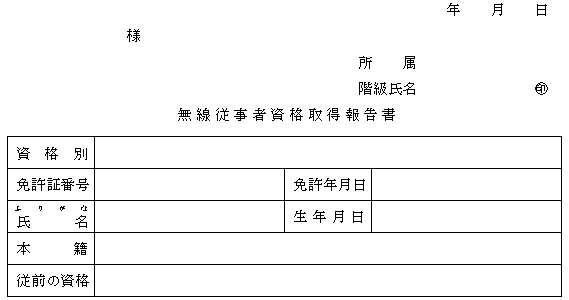 様式第6号
様式第6号
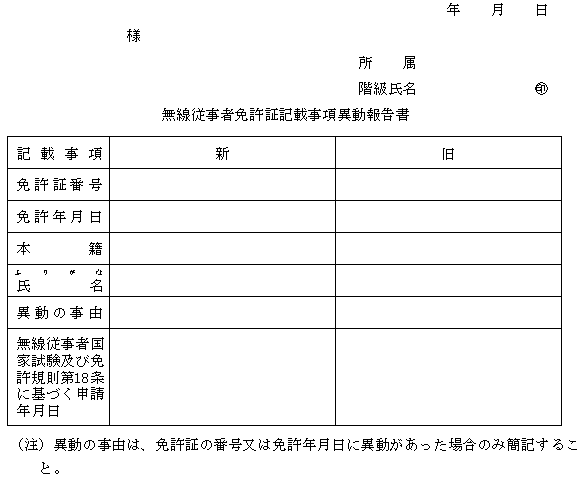 様式第7号
様式第7号
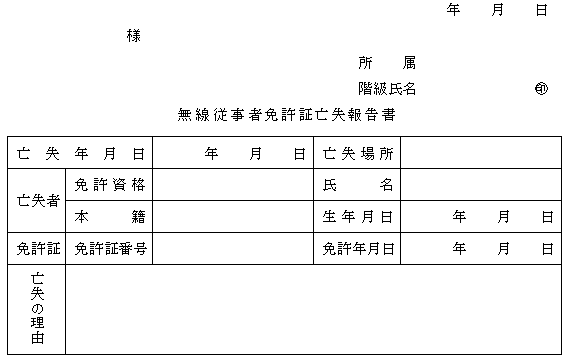 様式第8号
様式第8号
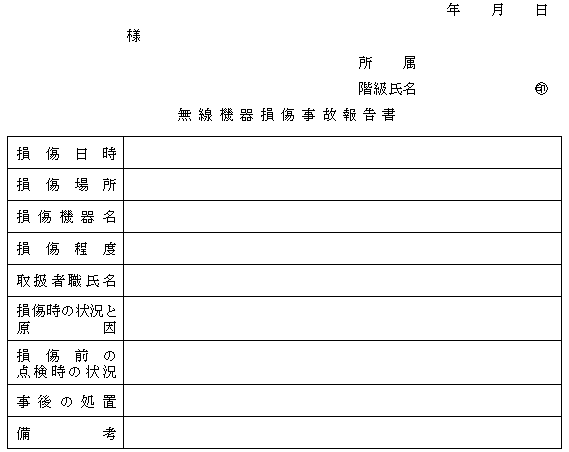 様式第9号
様式第9号
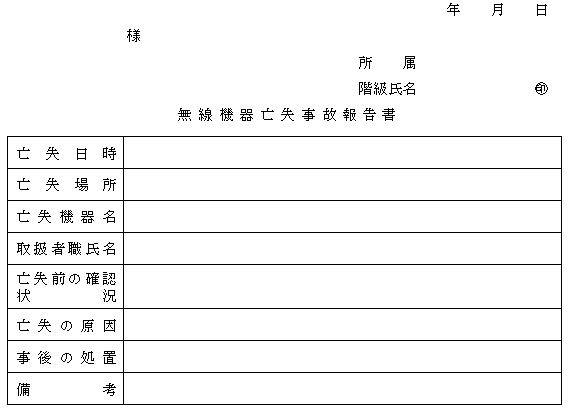 様式第10号
様式第10号
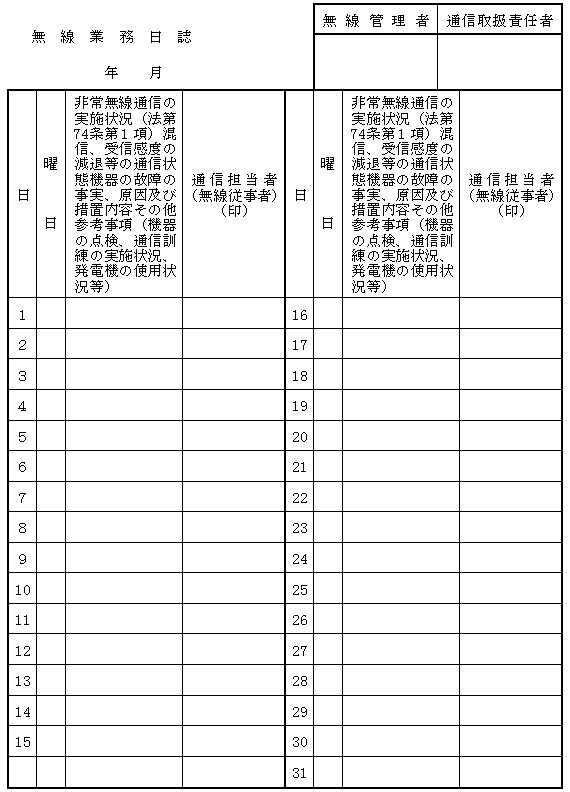
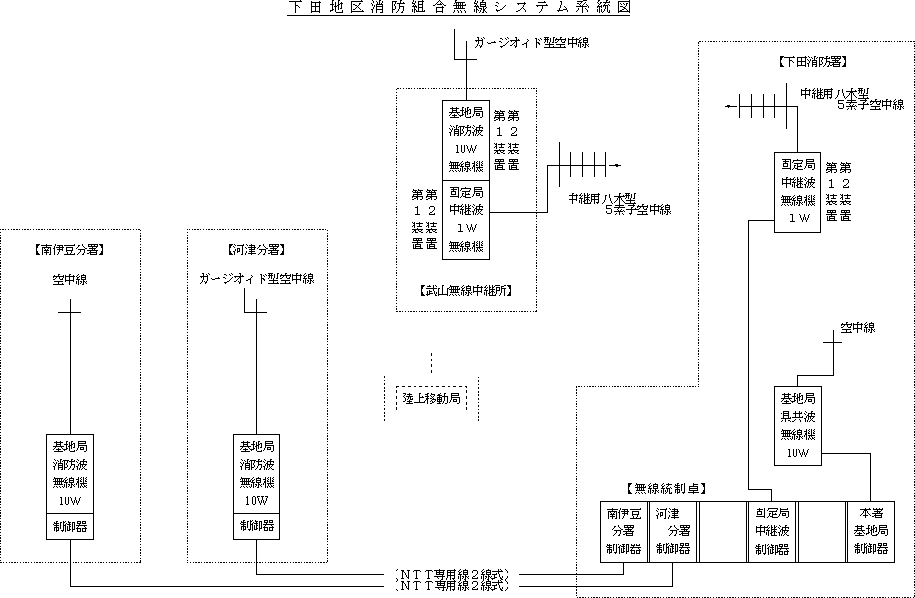 別表第2(第19条関係)
通信統制時における内容制限
別表第2(第19条関係)
通信統制時における内容制限別表第2(第19条関係) 通信統制時における内容制限
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号
様式第6号
様式第7号
様式第8号
様式第9号
様式第10号